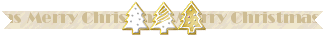
「中尉、今年もまた君が作ったケーキが食べたいんだが」
あと一週間ほどでクリスマスになろうかという時になって言われたセリフ。
私はそのあまりにも意外すぎるマスタング大佐の言葉に、思わず瞬きした。
「は?」
「うん、だからだな、ケーキを作って欲しいんだ」
にこにこと笑って、彼は言う。
どう見ても酔っているようには見えなかった。
まあ、勤務時間中に酔っぱらっていたら問題なのだが。
「中尉?聞こえてるかね?」
からかっている様子でもない。
どうやら本気らしい。
「はあ…あの…」
「ん?」
「まさか、去年のことをお忘れになったのですか?」
思わず聞いてしまう。
なぜなら、去年の年末に起きた災難を私は忘れていなかったからだ。
その時も大佐は私にこう言った。
『たまには君の手作りケーキを食べてみたいのだが、今年のクリスマスに作ってくれないか?』と。
その時、私は『無理です』と突っぱねた。
忙しくて作る時間などなかったし、それになぜ、私がそんな物を作らなければならないのか!
おいしいケーキ屋はイーストシティにもたくさんある。
そう言って断ったが、大佐はしぶとかった。
事あるごとにケーキの話をし、ついには仕事を片づけるのと交換条件、とまで言い出す始末だった。
これには私も怒った。
『ふざけたことをおっしゃらないでくださいっ』
『だが、中尉。これだけの量の仕事を片づけるのは気が滅入る作業なんだ』
『大佐ご自身の責務なのですから、仕方がありません』
『せめて、仕事を終わらせた後の楽しみがあってもいいだろう?』
『早く片づけば、早く帰宅して、ゆっくり眠れます』
『中尉…』
こんな会話がいったい何度繰り返されたことだろう。
結局、根負けしたのは私の方だった。大佐は条件に提示した期日通りに仕事を片づけ、私はクリスマスに合わせてケーキを作って出勤することになった。
しかし…。
「あの時、寝込まれたのをお忘れですか?」
端的に言うと、私はケーキを作るのに失敗したのだ。
見た目はまあまあ良かったが、朝、出来上がったそれを確認して、いざ家を出ようとして気がついた。
テーブルの上に砂糖壺と並んで塩の入った壺があることに。
形は同じだが、色が違う二つの壺。
ふだん戸棚の中にあるソレは料理の時しか出すことはなく、ちなみにケーキ作りの材料に塩は必要ない。
前日、かなり疲れた状態で適当にケーキを作ったのは確かだった。
だからといって、まさか…とは思った。
『………』
しかし、真相を確認する時間的余裕はなく、仕方がないのでそれを持って出勤し、大佐に説明した。
大佐は悪い冗談だと笑ったが、一口食べたところで彼の顔は凍り付いた。
休憩がてら、一緒にお茶にしたハボック少尉たちも同じ反応だった。
私も口元を押さえる。クリームは悪くない。問題は土台に使われているスポンジにあった。食べる者の期待を裏切る微妙なハーモニーは、もはや犯罪的。
『すみません、やはり捨てます』
迷わず、そうしようとした私の手を押しとどめ、
『いや、食べる』
大佐は無表情のまま、少尉たちの残した分もすべてたいらげたのだった。
そして、ごく自然の成り行きとして、調子を崩し、倒れた。
その後、慌ただしい年末に向けて東方司令部内にも多大な支障が出たのはもはや言うまでもないことだろう。
「ああ、もちろん忘れてはいないさ。中尉」
「でしたら…」
「だが、おいしかったからな」
「は!?なんの冗…」
「いや、だから、中尉が看病をしてくれた時に作ってくれたおかゆとか」
「…っ」
「だから、料理が上手なんだというのはわかっている。去年のケーキはまあ、運がなかったということだな」
大佐が女性にもてるというのがよくわかるセリフだと思う。
こんな風に言われたら、いくらでも彼が言うように作ってあげようという気になるのだろう。…というか、そうなりかける自分を私は内心、叱咤した。
「いいえ、私は作りません。大佐がなんと言われようと、です」
あんなことがあって、もう二度と大佐のためにケーキは作らないと決めたのだ。
私が作らなくてもおいしいケーキはどこにでもあるのだから、どうしても食べたいならそれを買ってプレゼントしてもいい。
大佐はそんな私を見て、呆れたように息をつく。
「まだ気にしているのか?」
「それは…否定しません。しかし…」
「わたしは君が作ってくれたものが食べたいんだ」
「…っ」
「わかってくれたかね?中尉」
笑って覗き込んでくる瞳に、戸惑いを浮かべた私の顔が映り込んでいた。
顔色までは読み取れないが、頬の熱が上がったのは感じる。
それを誤魔化すために、「まるで口説き文句みたいですね」と言うと大佐はがっくりと肩を落とした。
彼は何か言おうと口を開きかけたが思い直したように、息をついた。
「大佐…?」
「ああ…まあ、気にしないでくれ」
「はあ…」
「とにかく、そういうことだから、23日は一緒に帰ろう」
「………は?」
「シフトの都合上、この日なら一緒に帰れそうだからな」
「いったいなんの…」
「一人で作って失敗しそうなら、二人で作ればいいわけだろう?」
「え…?」
「ん?だから、わたしが手伝うと言っているんだ。名案だろう!」
「……いえ、あの、大佐っ」
何かが間違っている気がした。
そもそもいったいいつの間に、今年もケーキを作ることになったのだろうか。
「やはり、ケーキはお店で…」
「なんだ、君はわたしの作るケーキが食べられないというのかね?」
ちょっと気分を害したように、大佐。
「い、いえ、そういうわけではなくてですね…」
反射的に慌ててそう言うと、大佐は嬉しそうな笑顔を見せた。
その笑顔は反則技に近い。
「だったら、問題はないだろう?」
問題はなにやら山積みのような気がした。…気がしたが、この理解しがたい理屈と展開をくり広げる相手には何を言っても無駄のような気もした。
それにきっと去年と同じような会話を繰り返すハメになったら、どうせ根負けするのは私なのだろうと思った。悔しいけれど、たぶんきっとそうなる。
そう思うと、反論する気がいっきに失せてしまった。
「一緒にケーキを作ろう」
やけにはりきった口調で言う大佐の様子に私は苦笑するよりない。
でも、このままでは終われないのも確か。
反論できないかわりに、ささやかな一矢を報いておこう。
「別に作るのはかまいませんが、それですと23日は残業できませんね」
「もちろん、その日は残業しなくてすむように仕事は終わらせる」
「そうですか。その希望的観測がかなうといいですね、大佐」
言いながら、私はにっこり笑ってみせることも忘れない。
そこで大佐はハッとしたように私を見たけれど、これ以上、彼と言い争う気はなかった私はさっさとその場から退散した。
そうして、私はスケジュール手帳に次の一文を追加する。
『23日の予定:大佐とケーキ作り、もしくは、徹夜で残業』
|
|