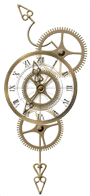
『見てはならぬモノを見てしまった』
…というより、
『見たくはなかったモノを見てしまった』
なんてコトがあった次の日は、朝から心身共に曇り気味。
吸いなれた煙草の味さえマズく思えて、ハボックは手のひらでごしごしと顔をこすった。
実は睡眠不足でまぶたが重い、なんてのも、その原因を考えるとひどく腹立たしくて仕方がない。
そして、その原因の主は本日、欠勤。
今現在、彼がいったい何をしているのかなど考えたくもなかった。
なのに、自然とそれしか考えられなくなる自分がとてつもなくイヤだった。
『所詮、他人事だってーのに』
身近でよく知る二人の問題になるわけだが、こーゆうことはお互いで解決してもらうしかないわけで。…もしかしたら、既に解決済みなのかもしれないし。
とにかく、第三者の自分がしゃしゃり出ることじゃないのは確かだと思う。そう思いはするのだが。
「調子が悪そうね?少尉」
ふいに響いてきた声に、彼はドキリとした。
場所はマスタング大佐の執務室。部屋の主がいないため、手伝いに借り出されたハボックは自然、ホークアイ中尉と二人で書類整理に励んでいた。
そんな風に同じ部屋にいるのだから声をかけられるくらい当たり前のことだとわかっていたのに、この時、彼は胸を錐で突かれたような衝撃を覚えた。
「ええ…まあ、ちょっと」
曖昧に応えて、押さえたのは腹。
それが演技で済めば問題なかったが、本当にぐぐうっと外から圧力を受けたような圧迫感を感じたのだから始末に負えない。
『オイオイオイオイっ!勘弁してくれ!!』
他人の色恋沙汰に首を突っ込むなんて面倒ごと、とてもじゃないが、ご遠慮申し上げたい。
しかも相手は軍部内でも焔の錬金術師として名を馳せるマスタング大佐と、女性ながらも彼の片腕とも称されるホークアイ中尉なのだ。
彼らのケンカは高見の見物で済ますには面白いが、その渦中に飛び込んで無事に生きて戻れる可能性は低いに違いなかった。
それでも…。
「そんなに具合が悪いのだったら、医務室に行ってきていいわよ。少尉」
金の髪をきっちりまとめ上げたホークアイ中尉の、気遣うような声にハボックはのろのろと顔を上げた。
他人にも自分にさえも厳しい人だが、他人を気遣う優しい一面も彼女は確かに持っていた。彼女をよく知らない者が見れば珍しさに驚くだろうが、近くにいれば自然とわかる。元々やさしい気質を持っているのに、彼女は必要な時しかそれを表に出さないのだと。
「本当に顔色が悪いわよ?」
「そっすか…?」
「ええ。熱だけでもここで計る?」
すぐさま目の前に差し出された体温計に、ハボックは力なく苦笑した。
断るタイミングと気力を失い、素直に受け取った体温計を脇の下に挟むことにする。机の上にコトリと置かれた砂時計といい、本当に中尉は手際が良いうえ、面倒見が良い。
「…………」
『なんで俺がこんなダメージ受けてんだよ、オイ』
自分自身の愚かさに盛大なため息が漏れた。
あまりの疲労感に煙草を持っているのもだるくて、灰皿に押しつける。
この疲労感も、心身共にくるダメージも、すべては中尉が『良い人すぎる』からに違いない。
こんな彼女がアノ上司に裏切られているかもしれないと思うから、はらわたが煮えくりかえるような、それでいて、もどかしさにイライラするような…おかしな気分になるのだ。
強い女性に見えるが裏切られたと知ったら、やはりきっと傷つくはずだ。
『クソッタレ!』
絶対、大佐の方が中尉にベタ惚れで、彼女なしでは生きていけないくらい依存度も高いと思っていたのだが…。
「そーいや、大佐が休みってまた急な話ですね…」
「あら、急でもないわ。ずいぶん前から今日のことを言っていたのだけど、シフトや仕事の都合があったから。でも昨日までに…正確には昨日のお昼を少し回ったくらいかしら?それまでに必要なことはすべて片づけて早退して行ったわ」
「…それだけ大切な用事でも?」
ずいぶん前からということは、突発的なモノではなく、計画的犯行なのか。
ハボックは自分の心臓がイヤな感じに早くなるのを感じた。
しかし、ホークアイ中尉はといえば、
「さあ、私はそこまで知らないから」
いつもと同じ様子で気のない風に応え、砂の尽きた砂時計を取り上げながら、片手を差し出した。
一瞬なんのことかわからず首を傾げそうになったハボックだが、ハタと思い出して体温計を中尉に返す。
「平熱ね。でも、まだ気分が悪いなら医務室で薬をもらってくるといいわ」
凛とした声は本当にいつも通りで。
そのまま仕事の続きに戻ろうとする姿に、不安をかき立てられる。
「その、中尉…」
「?」
「ここんとこ大佐に何かヘンなとことかなかったッスか?」
これを言うにはかなりの勇気が必要だった。
大佐の恨みを買う云々よりも、面倒な他人事には関わらないという自分のポリシーを裏切るのだ。
しかし、中尉は小さくクスリと笑っただけで。
「別に。まあ、時々、挙動不審なトコロがあるくらいかしら?まずロクでもないことを企んでるのは確かね」
『そこまでわかっていて、どーしてそんなに平然としてるんスか!?中尉』
喉元まで出かかった言葉を、彼はなんとか押しとどめた。
ロクでもないこととはいえ、まさかアレほどロクでもないとは思ってもいないに違いない。それともやはり二人の関係は終わっているのだろうか?
『まさかっ!そんなことはまずあり得ない』
「あの、ロクでもないって…?」
「あまり考えないようにしてるの。ただ関わりにならないように極力、注意してはいるわ」
「それじゃ、なんの解決にもなりませんって!」
今度はさすがに声に出ていた。
そして、中尉の腕を掴む。
「行きましょう!中尉」
「えっ?行くって…」
戸惑う中尉を半ば引きずるようにして、司令部の外に連れ出す。
しかし、こんな時でも平常心を失わず、門兵に外出届を出す中尉はさすがであった。
「どういうつもりなの?ハボック少尉」
少し責めるような口調よりも、彼はタイムリミットの方が気になった。
「オレもまだはっきりとはわからないんですが、手遅れになるよりマシでしょう。行けばわかると思います」
と返して、中尉の腕を掴んで走り出す。
そして。
息を切らしてたどりついた教会の扉を開ける。
がらんと人気のないそこで彼らを待っていたのは、黒のタキシードを嫌味なく着こなした男の笑顔だった。
|
|